コンパクトシティとは、その名の通り小さくまとまった都市のことを指します。生活費を抑えながら豊かに暮らせるため、国ぐるみでコンパクトシティの形成が進むほか、コンパクトシティで暮らしたい人も増えています。
ここからは、コンパクトシティとは?コンパクトシティで暮らすメリットは?という疑問に答えていきます。
コンパクトシティとは?

「コンパクトシティ」は、海外で1970年代から提唱されてきた街のあり方の1つです。「住まい」と「生活機能」が近く、商業・交通などのインフラがコンパクトにまとまった都市がコンパクトシティに当てはまります。
コンパクトシティの歴史において起点といわれるのが、1972年に示されたマサチューセッツ大学「成長の限界」という研究です。研究では、このまま人口が増加することで、2072年までに地球は維持できない状態となってしまうという論文です。
これをもとに、ヨーロッパ、アメリカ、日本ではコンパクトシティの考えが広がりました。
日本では、法律の整備が進むなど、国単位で「コンパクトシティ」を進めています。
コンパクトシティの定義
コンパクトシティに人口や規模などに明確な条件はありません。
・自家用車なしでも生活できる公共交通を軸とした利便性の高い街
・インフラや行政コストを抑えて運営できる省エネな街
・環境や社会的弱者への配慮がなされた包容力のある街
こうした都市を「コンパクトシティ」と定義する動きがあります。またアメリカでは1973年に物理学者のジョージ・バーナード・ダンツィーグが提唱した「ニューアーバニズム」という言葉を用いることもあります。またイギリスでは「アーバンビレッジ」という呼び方もあるようです。
一方でコンパクトシティの逆を表す言葉に「スプロール化」という言葉があります。鉄道網が貧弱で車なしで生活できない街、まばらに開発され野放図に広がった街などが該当し、未来の少子高齢化社会に対応できない街です。
なぜコンパクトシティなのか?

高度経済成長期の人口増加を受けて、日本の都市圏では急速に住宅が拡がりました。これによりインスタント料理のような街、インスタント料理のような家ばかりになり、人口が減り始めたことで街の魅力が徐々に下がっています。
これからの家探し、街選びでは「コンパクトシティ」という考えを持たないと、空き家だらけの街に、インフラの維持費ばかりが高くなり、税金は高く、生活しにくいという、苦しい生活を送らなくてはなりません。
日本ではまもなく、住宅のうち30%が空き家になろうとしています。そこで重要性を増してくるのが、コンパクトシティの形成です。コンパクトシティに暮らすメリットは次の章で詳しく紹介します。
【メリット】コンパクトシティに暮らすべき理由

この章では、コンパクトシティが注目を集める理由や、コンパクトシティに住むべき理由を解説します。
少子高齢化が進んでいるため
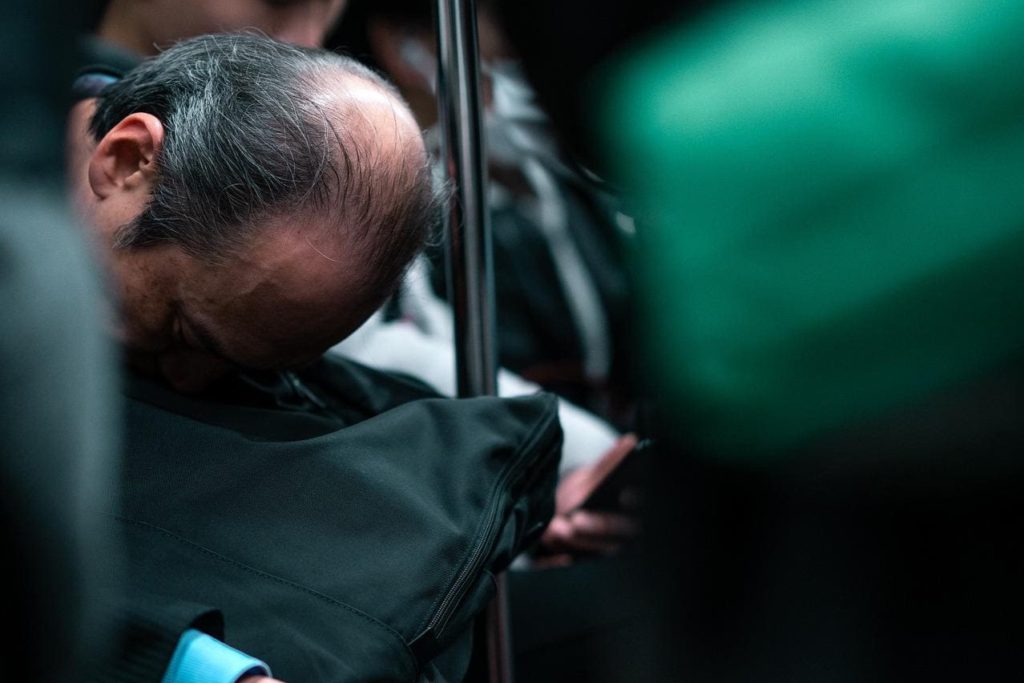
大前提として日本は人口が減っています。これまで100軒の家が必要だった街は80軒で済むようになります。さらに人口流入の続くエリアは大規模な集合住宅が建っており、人気を集めています。
こうしたことから、日本においてはかつてほど広い街が要らなくなりました。少なくとも令和時代において、都市を拡大する意味は全くありません。
そこへ、高齢社会がやってきました。これまで以上にバリアフリーをすすめ、介護・医療のインフラを集中させる必要が出ています。もしかすると徘徊・認知症などの対策、孤独死対策、葬儀インフラもさらに充実させる必要があるかもしれません。
こうした場合、生活が徒歩で完結し、すぐ病院にたどり着けて、隣近所との交流が便利なコンパクトシティの意義が高まります。
災害に対応するまちづくりが期待できるため
改正都市再生特別措置法では。災害リスクの高い災害ハザードエリア「レッドゾーン」への開発を禁止し、災害リスクのやや高い「イエローゾーン」では住宅等の開発許可を「厳格化」しています。
一方でこうして住民を比較的安全な立地に誘導し、地震や水害などの災害リスクから住民を守るためにコンパクトシティが推進されています。
さらに、都市が小さくなることで、救助や避難、助け合いなどの取り組みやすさが高まります。
生活費が抑えられるため
コンパクトシティが進間なかった場合、住民1人あたりの道路・下水道等のインフラ維持費用は2倍になります。富山県富山市が2004年に、人口密度が半分になった際の試算を行い、明らかになりました。
一方でコンパクトシティでは、
・インフラの維持費が最低限でよくなり、税金や光熱費などが安くすむ
・車を持たずに済み、交通費などの出費が抑えられる
・将来的に家を高く売れる
・時短で生活でき、浮いた時間を活用できる
まず自動車の維持が必須でなくなること。購入費用に加え、年間10万円程度の税金・保険、同じくらいのガソリン代、さらに駐車場代を考えると、給料の1~2ヶ月分を自動車関連で持っていかれるという世帯は少なくありません。これが要らなくなるのは家計にとって大きなプラスです。
さらに、コンパクトシティでは人口減少による空き家や犯罪などの影響が抑えられ、駅やバス、スーパーや病院、学校が近くまとまっているといったメリットも残ります。そのため家の資産価値が落ちにくく、引っ越す場合も元の家を高く売れます。
また、買い物や通勤にかかる時間が短くなることは、時間コストの節約に繋がります。例えばお弁当を作ってから出かける、1時間ゆっくり余分に寝る、副業するなどの暮らしができるのはコンパクトシティの特権です。
税金を抑え、出費を減らし、有意義な時間を増やす。コンパクトシティにはそういったメリットがあります。
【デメリット】コンパクトシティの推進が遅れている理由とは

一方、コンパクトシティは万能薬ではありません。デメリットとして、下記のようなことが考えられます。
人口が密集し住環境が悪化する
持ち家住宅の延べ床面積を都道府県別に比較した際、最も狭いのが東京、ついで神奈川、大阪、沖縄と続きます。一方で家の広い県は富山、福井、山形となります。
都市化が進んだ地域や土地の狭い地域ほど家が狭くなる傾向にあることから、各地に小さい都市を作ることが目標となる「コンパクトシティ」において、居住面積は狭くなる傾向にあるでしょう。
また、並行して、家賃の上昇やご近所トラブルなども増加しそうです。
大規模な災害時における物資不足
コンパクトシティの取り組みは、基本的に災害対策につながります。ただし、都市に暮らすということは、生活必需品を物流に頼る必要があるということでもあります。
都市部に住んでいる方なら、台風直撃の前夜などでスーパーやコンビニからパンやラーメンがごっそり売り切れている光景を見たことがあるのではないでしょうか。
災害の一時被害に強くなるコンパクトシティですが、二次被害を防ぐためには、都市計画の時点でどれほど備蓄をし、どう食料や水、電気を補給するかといったインフラを考える必要があります。
コンパクトシティ形成のための初期費用
行政が本気でコンパクトシティを推進する場合、自動車通勤からのシフト、空き店舗の活用、引っ越し補助など、様々なサポートを官民で実施する必要があり、経費もかかります。
さらに、人口を中心地に集める場合、高い地価・物価のエリアに、収入の少ない世帯が流入することが考えられます。
引っ越す人にとっては、まず引越代と物件を取得する費用がかかります。さらにコンパクトシティの外から引っ越す場合は、既存の家を売却する必要があり、場合によっては残置物撤去などの費用がかかります。
都市開発の妨げに
付け加えて言えば、こうしたコンパクトシティ化は、既存の経済をピンポイントで攻撃します。
たとえば、日本では1990年代から、大規模小売店舗が建設可能となり、田舎に「イオン」や「ららぽーと」が出来、大儲けしています。コンパクトシティを推進する場合、こうしたお店を経営している人にとっては、損しやすいと考えられます。
これからコンパクトシティで「賢く、安く」生活したい人にはメリットでも、これまで「自家用車で遊びに来て散財してもらう」というビジネスモデルで拡大してきた会社には、損失に繋がります。こうしたチグハグが、コンパクトシティ推進の大きな足かせになっています。
詳しくは「コンパクトシティの課題ー日経の報道をもとに」でまとめています。
コンパクトシティ事例
コンパクトシティの事例については、こちらの記事でまとめています。
まとめ:「コンパクトシティで暮らす」が未来では当たり前に
コンパクトシティのメリットは、「節約しながら豊かに暮らす」という、賢い暮らしを求める人にとっての必須要件を満たしていることです。
これから引っ越しや物件購入を考えている場合、その街が「コンパクトシティか?」という視点は、場合によっては出口戦略にもつながるため、かなり重要になります。
参考文献
https://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXMZO3109860029052018000000
https://www.mlit.go.jp/common/001295508.pdf
https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2008/
https://todo-ran.com/t/kiji/11967
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page17.htm
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE248CG0U2A121C2000000/
https://www.city.akita.lg.jp/shisei/iken/1003667/1020432/1036480/1036492.html






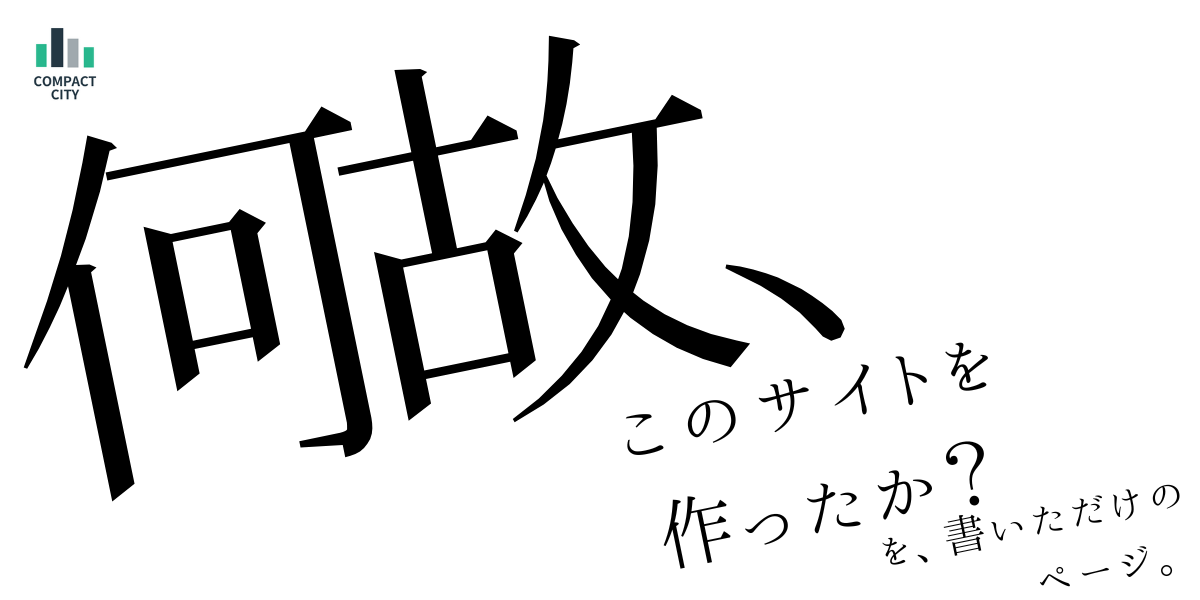
[…] コンパクトシティのメリットや実例は、こちらに詳しく書いていますが、これからも広がっていくでしょう。 […]
[…] 方都市でコンパクトシティが進展しないのか?という視点で、行政・企業・住民それぞれの視点から紹介します。なお、コンパクトシティのメリットについてはこちらで紹介しています。 […]
[…] コンパクトシティのメリットについてはこちらで解説しています。 […]
[…] コンパクトシティとは?メリット・デメリットと国内事例を専門メディアが徹底解説 「コンパクトシティ」は、海外で1970年代から提唱されてきた街のあり方の1つです。「住まい」と「 […]
[…] コンパクトシティとは?専門メディアが徹底解説 海外で1970年代から提唱されてきた、コンパクトシティ。日本でも少子高齢化が進む中で、度々議論されてきた、サスティナブルで新し.. […]
[…] 【関連記事】「コンパクトシティ」の解説 […]
[…] 【関連記事】そもそもコンパクトシティとは? […]
[…] 【関連記事】「コンパクトシティ」の解説 […]