近年駅前にタワーマンションが建つ場所が増えています。東京のど真ん中のような場所だけでなく、葛飾区や町田市のようなちょっと外れの街に建ったと思えば、岐阜や山形のような田舎町にポツンと1棟、という景色も。
このタワマンが増えることは、コンパクトシティにとって有利なんでしょうか。
タワーマンションとコンパクトシティの定義

そもそも「タワマン」とは何なんでしょうか。東京などの都市部に住んでいればぼんやりとイメージが浮かぶかもしれませんが、明確な定義がどのように決まっているかは知られていないのかもしれません。
タワーマンションは「超高層マンション」の俗称で、明確な定義はありません。日本マンション学会「マンション学事典」によると、建築基準法第20条-1「高さが六十メートルを超える建築物」をタワーマンションとしています。これはだいたい20階建てに相当しており、20階以上の建物を「タワーマンション」と呼ぶ傾向にあるようです。
とはいえ20階建てのいわゆる「団地型」の建物をタワマンと呼ぶ人は限られます。一方で18階建てなど基準に満たないマンションでも「◯◯タワー」という名前がつくこともあるでしょう。
一方でコンパクトシティはどのように定義されているかと言えば、
・自家用車なしでも生活できる公共交通を軸とした利便性の高い街
・インフラや行政コストを抑えて運営できる省エネな街
・環境や社会的弱者への配慮がなされた包容力のある街
こうした都市を「コンパクトシティ」と定義する動きがあります。

タワーマンションがコンパクトシティと言える理由

タワーマンションがコンパクトシティになりうる理由には、タワマン特有の「集約」という要素が挙げられます。
1棟に1000人が暮らす「集住」
タワマンの多くは300世帯ほどが入居します。仮にそこに、2LDKが100、3LDKが200部屋あり、それぞれ2人家族と4人家族が入居したと仮定すれば、そこは1000人が集う街になります。立派な村と言えます。それらが大きめのスーパーマーケットくらいの面積に集住します。これによるメリットは大きいでしょう。
例えば仮に、街のハズレに住んでいた世帯が駅周辺のタワマンに引っ越してきただけで集住率が変化する可能性もあります。タワマンが駅周辺に3~4棟建てば、そこは立派な人口集中地区になります。
住宅と都市機能が近接
タワマンは駅近くに作られる場合が多く、その周辺や低層階には商業施設や公共施設が入り、エレベーターで簡単にアクセスできます。利便性を享受しやすい環境です。
インフラという意味では、タワマンによって人口誘導が進むことで、これまで費用のかさんでいたインフラ維持の資金を、さらなる都市の改善や減税という形で住民に還元できるようになります。例えば300世帯がディズニーランドの敷地に広がっているのと、東京ドームの敷地に広がっているのを比べれば、どれほど水道や電気の配線、道路やインターネットの維持が楽になるか想像がつきます。また雪国であれば雪かきが不要になります。
タワーマンションがコンパクトシティと言えない理由

一方で、コンパクトシティを推進する動機の1つである「災害」には弱いのがタワマンの弱点です。
有事の弱さ
高層建築の場合、上下移動が発生します。人間は横方向の移動であればどうにでもなりますが、縦方向の場合はこどもや高齢者にとって大きな負担となります。ましてや車いす、寝たきりなど、障がいを抱えているならなおさらです。
例えば地震や台風に耐えても、その後のインフラが復旧するまでの間、エレベーターが使えないということも考えられます。30階や40階に住んでいた場合、帰宅・居住そのものが難しくなるでしょう。
高層階は「救助」が難しい
また低層階で火災が起き、万が一燃え広がった場合、高層階はどのように避難できるのか、未知数です。タワマンは基本的に燃えないように作られているとは言え、「絶対」とは言い切れません。タワマンは60メートルを超える建物と先程書きましたが、はしご消防車は届いて40メートル、避難は簡単ではありません。
サスティナブルではない
コンパクトシティの1つの意義として、住み続けられる街を形成するという要素があります。
コンパクトシティにはこれまでかかってきた都市開発や道路整備が不要になるという環境面のメリットがありますが、タワマンは大規模な開発が必要な上、その建物の寿命は70~100年程度と言われています。
2世代程度ならなんとかなりますが、世代を重ねるごとに修繕積立金が高くなり、空き家が増え、建物が老朽化したとなれば、再び大規模なスクラップアンドビルドが必要になります。
タワマンはコンパクトシティの切り札だが

タワマンが建つことで、住民が集住し、商業の誘致が起こり、近隣に賑わいが生まれる…そう考えた場合、タワマンはコンパクトシティ化への切り札のように見えます。
しかし、ここまでで書いてきた通り、タワマンはコンパクトシティの要件を満たすものの、理念を体現したものではないと言えます。
タワマンを建てればすべて解決にはなりません。せっかく呼び込んだ住民らが街に出たくなる、商業・公共施設はどうしても必要です。まず街に繰り出してもらう。そこで地域の人と交流しない限り、どこの街に暮らしていても楽しくないのは一緒です。建物にプラスして、暮らし方を提案する必要があります。
さらに、これはあくまで、数十年単位の短期・中期的な視点です。タワマンは概念自体が新しく、1976年の「与野ハウス」(住友不動産)を皮切りに1990年代から徐々に数を増やし、2010年代に市民権を得てきた建物です。
現段階で50年持ったとしても、その後の高い管理費や、壊せるかもわからないビルが、毎年のように起こる台風や地震に耐え続けられるのか。そういった観点から、階段+エレベーターしか移動手段がなく、災害時に万事休すとなってしまうタワマン頼みのまちづくりは、慎重になる必要があると言えるでしょう。
参考
「ここに住みたい」と誰もが願う都市の「新しい基準」とは
https://news.mynavi.jp/article/20221219-2538275/コンパクトシティを再考する―最近の動向を踏まえて― 筑波大学大学院
https://www.lij.jp/html/jli/jli_2013/2013spring_p001.pdfタワーマンションの歴史
https://www.stepon.co.jp/premier/mansion_history/tower.html「タワーレジデンス甲府中央」(10階建て)
https://www.homes.co.jp/archive/b-14529316/




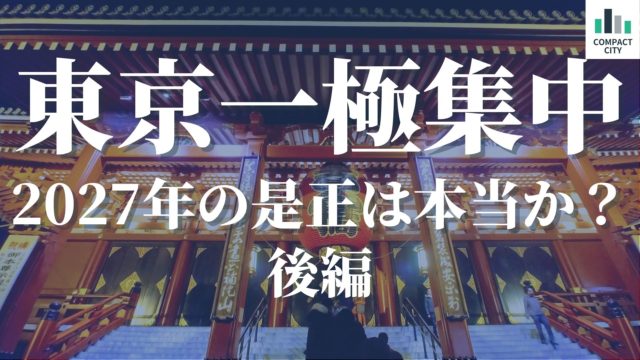
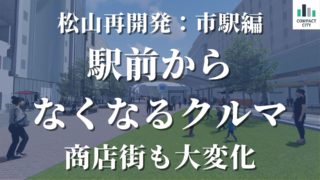
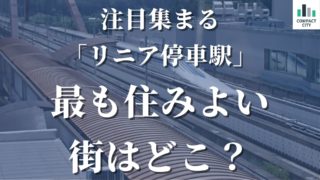
[…] かつて「タワマンはコンパクトシティか」という記事を書きました。コンパクトなまちづくりに貢献するタワーマンションですが、持続可能性という意味では疑問。都心の一部では「定 […]