世界のコンパクトシティと言いながら、日本の情報が中心ですが…今回からコンパクトシティの入門書「世界のコンパクトシティ 都市を賢く縮退するしくみと効果」を要約解説します。まず第一章の内容をもとに、解説します。
コンパクトシティの定義とは
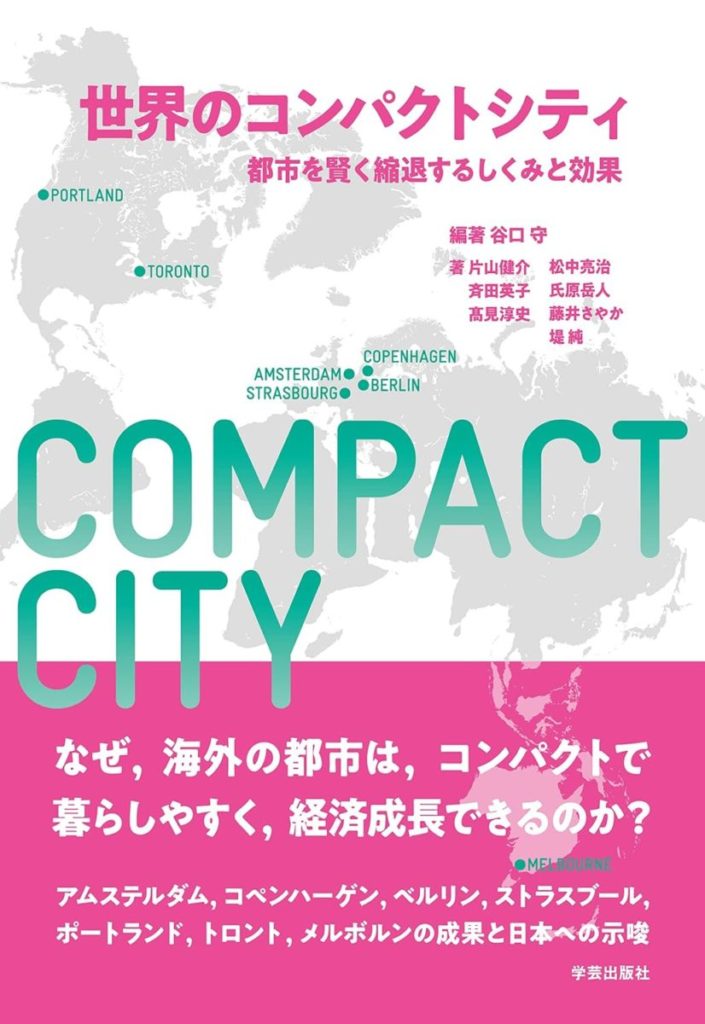
まず、コンパクトシティとはなんでしょうか?
明確な定義は決まっていませんが、イメージとしては言葉の通り「まとまった街」を作る試みです。自動車がないと暮らせないような街をやめ、街の中心地を元気にすることで「強中心型都市圏」をつくります。
強中心型都市圏
「強中心型都市圏」では、電車やバスなどの公共交通が街の中心に繋がり、駅周辺で高密度な暮らしができます。
すると、わざわさ車に乗らなくても仕事ついでに買い物を済ませられたり、通勤通学通院が早くなったり、いろいろ便利になります。
さらに、徒歩と電車が移動手段のメインになることで、CO2排出量は減ります。実際、人口密度が高い街のほうが自動車の二酸化炭素排出量は少ないとされています。山を削って街を作る必要もないため、実際はもっと環境に良くなります。
ほかにも、インフラ全般が効率的になったり、人が駅周辺に集まることで街が賑わったりと良いことがたくさんあります。
引用:「多様化するコンパクトシティ政策がもたらすクロスセクターベネフィットの可能性」
世界のコンパクトシティの歴史とは

コンパクトシティの概念は50年前の1973年から提唱されてきました。本格的に注目されるようになったのは1980年代後半から。「国連ブルントラント委員会」の「私達の共通の未来」という発表により、持続可能性がある街こそコンパクトシティであるとして、話題になりました。
以降、ヨーロッパを中心に「環境」の面でコンパクトシティが広まります。
一方で、車社会のアメリカや、まだイケイケだった頃の日本でコンパクトシティの概念が広まるのは遅れました。日本でコンパクトシティが法制化されるのはヨーロッパから20年遅れの2012年。
「エコまち法」(正式名称:都市の低炭素化の促進に関する法律)が制定されました。
また、2014年には都市再生特別措置法により「立地適正化計画」策定が可能に。現在、立地適正化計画が進んでいる街は675団体(2023年、国交省)。1718の自治体がある中で3分の1以上はこの計画を策定しています。
日本のコンパクトシティの課題

一方で、都市の中の「交通」を支援する手段が薄いこと、法律だけが整備され、人手などの実務に課題が残る点が課題として浮き上がります。
また、単純に高密度住宅を建てることイコールコンパクトシティではないということも注意です。
かつて「タワマンはコンパクトシティか」という記事を書きました。コンパクトなまちづくりに貢献するタワーマンションですが、持続可能性という意味では疑問。都心の一部では「定期借地権」という仕組みを用いて50~70年後に壊すことを前提としたタワマンも建ち始めており、どうしてもスクラップビルドが前提になってしまっているようです。
自治体単位だけでなく県、地方単位での意識のすり合わせも必要です。先述した立地適正化計画が自治体単位で策定された以上、近隣の街とどこまで意思疎通を測った上で作られているかわかりません。一方で横浜市や川崎市、大宮市など、東京圏との接続を前提に繁栄している街を見れば分かる通り、隣近所の街との関わりは都市において重要です。
これが無視されている以上、このまま立地適正化計画をすすめても、コンパクトシティができるのではなく、これまでどおりのまだら模様の街が作られ続ける危険性があると言えます。
課題の解決策

本のなかで、こうした課題の解決策としてあげられているのは下記6項目です。
1 公共交通を支援する
日本は公共交通のために公的資金がほとんど注入されていない。公共交通は横軸のエレベーターとして、公共交通の黒字化ではなく街の黒字化のために公共交通を活かすという考え方を持つ。ちなみに鉄道が必須というわけでもなく、バスだけで街の中心拠点が賑わっている丸太の首都バレッタという事例がある。
2 コンパクトシティは高層化でないという前提を心がける
高層ビルが林立していても、そこに郊外からクルマで通っていては本質的ではない。まちなかに人が住んで、まちなかで買い物や仕事ができるといった快適な環境整備が大切。
3 業務負担を減らす
人手不足や部署間の調整などがコンパクトシティづくりのハードルになっている。コンパクトシティ担当者をサポートする仕組みが必要。
4 広域的視点に立つ
自治体単位でなく、県や都市圏でのネットワークがあるという前提でコンパクトシティを作る。現在のバラバラな立地適正化計画ではなく、都市間のネットワークを無視しない計画にする。
5 階層的視点で捉える
都市と地方の連続性がいる。大都市拠点の周囲に中心拠点があり、地域拠点、生活拠点、小さな拠点が階層的に連なるような国造りを提案していく。
6 市街地の質を高める
人口密度だけでなく、社会基盤を整備する。コンパクトだけでなく暮らしやすい街を作る。
参考文献
世界のコンパクトシティ: 都市を賢く縮退するしくみと効果












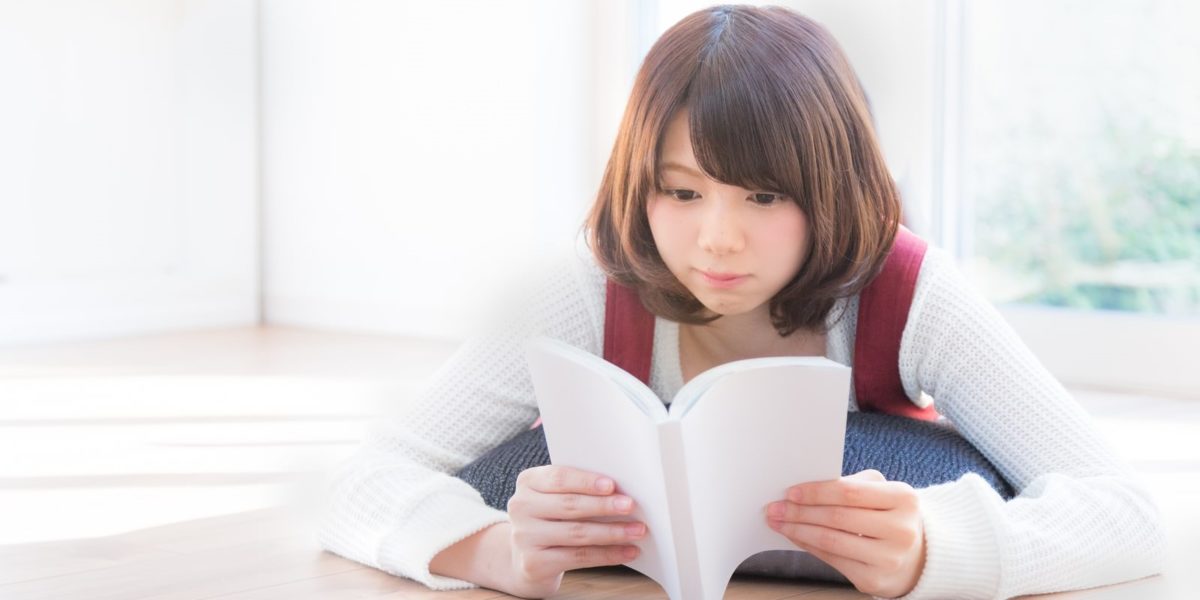
[…] こちらの記事で詳しく解説しています […]